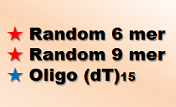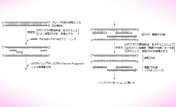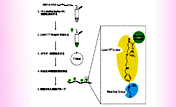Exo-free Klenow Type
製品説明
[α-32P]、[3H]dCTPを用いてDNAをラベルし、ハイブリダイゼーション用のDNAプローブを作製するためのキットである。FeinbergとVogelsteinの方法に改良を加えたもので、簡単な操作で高比放射活性のDNAプローブが作製できる。さらに、Random Primer DNA Labeling Kit Ver.2では、3'→5'exonuclease活性を除去したExo-free Klenow Fragmentと9 merのRandom Primerを組み合わせることで、1×109 dpm/μgの高比活性プローブを短時間(10分以内)で得ることを可能とした。
内容
(30回分)
| 1. | Random Primer(9 mer) | 60 μl |
| 2. | 10×Buffer | 75 μl |
| 3. | dNTP Mixture | 75 μl |
| 4. | Exo-free Klenow Fragment(2 U/μl) | 30 μl |
| 5. | Control DNA(λ-Hind III Fragment 25 ng/μl) | 10 μl |
保存
-20℃
注意
- 本製品は反応にrandom primerを用いているため、300 bp以下の鋳型DNAを使用すると取り込み率が低下したり、十分な長さのプローブが得られない場合があります。鎖長の短い(特に150 bp以下)鋳型DNAを使用する場合は、MEGALABEL(製品コード 6070)を用いた末端標識をお勧めします。
- GC含量が高い鋳型DNAあるいは高次構造をとりやすい鋳型DNAを使用すると、高次構造の影響で取り込み率が低下することがあります。そのような場合は、高温で反応できるBcaBEST Labeling Kit(製品コード 6046)の使用をお勧めします。
図1 Random Primer DNA Labeling Kit Ver. 2でのプローブの比活性と反応時間
テンプレートとしてλ-Hind III 断片25 ngを使用
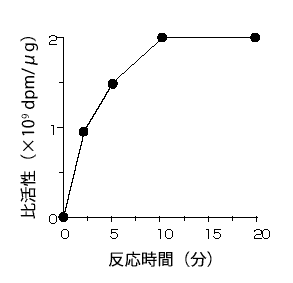
テンプレートとしてλ-Hind III 断片25 ngを使用
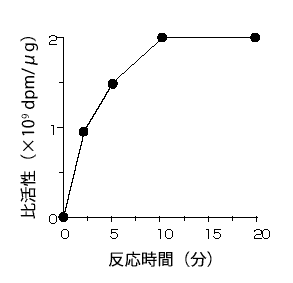
ランダムプライマーDNAラベリング法について
ハイブリダイゼーション法によりDNA中に存在する特異的配列を検出する際には、非常に高い比放射活性を持つDNAプローブが必要である。このDNAプローブ作製のために用いられるDNA標識法としては、従来はニックトランスレーション法が主に用いられていたが、このニックトランスレーション法には、次のような欠点があることが知られている。
1.放射性物質の取り込み率が比較的低い。
2.長時間の反応を行うと、DNA Polymerase I のexonuclease活性によりすでに取り込まれた放射性物質が遊離し、取り込み率が低下する。
3.鋳型となるDNAが高純度であることが必要である。
4.反応後に未反応の放射性dNTPを除去する必要がある。
1983年にFeinberg, A. P. とVogelstein, B. により発表されたランダムプライマーとKlenow Fragmentを用いてDNAの標識を行う方法は、これらの欠点を持たないDNA標識法である(表1)。その原理を図2に示した。鋳型DNAを熱変性により一本鎖DNAとし、この一本鎖DNAに対しランダムプライマーをアニールさせた後、Klenow Fragmentを用いて相補鎖合成を行う。このとき、dNTPの一つあるいは複数に〔α-32P〕〔α-35S〕〔3H〕等の標識化合物を用いると、合成される相補鎖が標識される。この相補鎖を熱変性により一本鎖とし、ハイブリダイゼーションプローブとして用いることができる。
表1 DNA標識法の比較
| ニックトランスレーション法 | ランダムプライマーDNAラベリング法 | |
| 反応時間 および 反応モニター |
長時間の反応により取り込み率が低下する。このため反応モニターを行い、取り込み率を測定する必要があ る。 | 短時間で高非活性プローブが得られる。また、長時間の反応を行っても取り込み率は低下しない。 |
| プローブの比活性 | ~108 dpm/μg | ~109 dpm/μg |
| 鋳型DNA中の不純物の影響 | アガロース等の混入によって反応が阻害される。 | アガロース等の混入によってほとんど阻害されない。 |
| 鋳型DNA量 | 1 μg程度 | 25 ng |
| 反応後の処理 | ゲルろ過による未反応dNTPの除去が必要。 | 反応液から未反応dNTPの除去をすることなくハイブリダイゼーションに用いることができる。 |
図2 ランダムプライマーによるDNA標識の原理
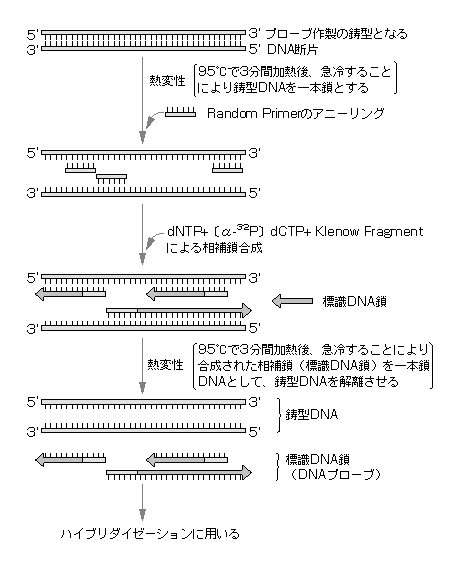
- 注意事項
- 本ページの製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
- タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
- タカラバイオ製品に関連するライセンス・パテントについては、ライセンスマークをクリックして内容をご確認ください。
また、他メーカーの製品に関するライセンス・パテントについては、各メーカーのウェブサイトまたはメーカー発行のカタログ等でご確認ください。 - ウェブサイトに掲載している会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。